| 左の写真は羅城門跡の看板。平城京の入り口でした。ここら辺一帯は羅城門があってその礎石も郡山城の石垣に使われています。 |
| 郡山城は筒井順慶のころに本格的に発展し、1580年松永久秀を倒した後、筒井から居城を移したのが郡山です。 筒井順慶のときにどのくらい工事が進んだのか良くわかっていませんが、多聞城から石垣の石を運んだり、明智光秀が見まわりに来たり、天守閣を急造した事などが記されています。そのためか、福知山城に良く似た構えをもち、石垣も野面積みで石塔、石地蔵が使用されたところも共通しています。 本格的な工事は1585年に豊臣秀長が100万石の大名にふさわしい居城にすべく大築城を始めたもので、現在残っている縄張りはできあがりました。 のち、秀長の養子秀保も1595年若死し、大和豊臣家は断絶してしまいます。その後、増田長盛が、20万石の大名として入りました。長盛時代は外回り惣掘、つまり外堀の工事をおこない、川の流れを変えるなどの工事を行いました。しかし増田長盛は西軍に属したため、1600年10月には本多正信、藤堂高虎といった徳川方に明渡し、取り壊されてしまい事実上、廃城になってしまいます。 のち代官として赴任した大久保長安が城地を預かることとなり、大和の安定をはかることとなります。その後、家康は筒井氏が伊賀没収された筒井定次の弟の定慶を一万石で郡山城番に任じました。 1615年大坂夏の陣がおこり、定慶は豊臣方の誘いを拒否したため攻撃をうけ、自刃してしまいます。 |
| 左の写真は羅城門跡の看板。平城京の入り口でした。ここら辺一帯は羅城門があってその礎石も郡山城の石垣に使われています。 |
| やがて、水野勝成が大坂の陣の後に郡山城主になり、6万石の大名として入城します。しかし当時の郡山城は荒廃著しく、復興を目指しますが、わずか5年後、備後福山10万石の大名として移ったので、松平忠明が12万5000石ので郡山に入ります。この頃にもう郡山城は復興が成ります。 |
| 五軒屋敷跡。歴代郡山藩の重臣たちが住んでいた場所で、松平忠明の時代に形が整います。5軒屋敷が並んでいたのでこの名が付いています。 |
| 1639年、松平忠明は姫路へ移り、かわって本多政勝が15万石で郡山に入りました。1671年、政勝が死去した後、跡目争いが起き96騒動と呼ばれ、もともと政勝の従兄にあたる政朝は実子であった政長が6歳だったため一時従弟の政勝につぐことになっていました。しかし政勝は実子の政利に継がそうと世継ぎにしてしまったために、政長と政利との間に争いが起こったのです。結局幕府により政長9万石、政利6万石とし落着しました。これが96騒動の名の所以です。 1679年政長が死去しその養子の忠国は15万石で奥州福島へ政利は8万石で明石へ移り、変わって松平信之が明石から8万石で郡山へ入ります。 信之在城7年で幕府の老中に任命され、1685年9万石で下総古河に移り、宇都宮より本多忠平が12万石で入部します。 |
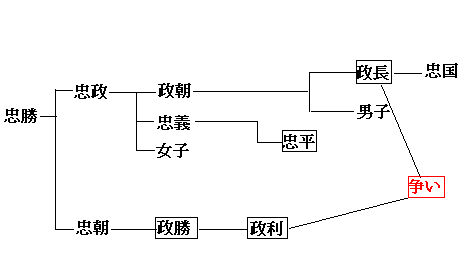 本多氏の系図 |
| 1723年本多氏が断絶し、翌年、柳沢吉里が15万石で郡山城主に任命され入城し、明治維新までの147年間在城します。 後、明治維新を迎え、廃城となりました。現在郡山城は県指定文化財となっています。 |
| 柳沢氏の菩提寺の永慶寺。この山門は郡山城の城門を移築したものです。市の指定文化財。 |